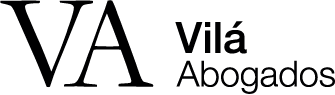2024年10月23日付、マルチラテラル・トレーディング・ファシリティ(多角的取引システム。以後「MTF」)における取引承認を申請する会社のための、複数の議決権付株式構造に関するEU指令第2024/2810号が、採択された。
まず、「MTF」とは、投資サービス提供会社、または市場統治機関によって運営される取引プラットフォームであり、金融商品の売買持分の一括契約を成立させることを可能にするものであることを明確にすることから始めよう。この概念には、規制市場と成長中の中小企業市場(市場に参加する金融商品の発行者の少なくとも50%が中小企業である市場)の両方が含まれる。同様に、「Tenure voting」(長期保有株主優遇する議決権行使制度)が当該指令の適用対象外であることも、ここで言及しておく。
本指令の前文(解説部)には、複数議決権行使のメカニズムは、一つの資金調達手段として、中小企業の取引プラットフォームへの上場取引をより魅力的にすることを目的とすると記している。つまり、中小企業の上場自体や、もしくは株式所有権の絶え間ない取引を奨励することではなく、中長期的に安定した形で会社に関与する投資家の参入を可能にすることが目的である。これまでは、創業者あるいは支配株主の、会社のコントロールを失ってしまうかもしれないといった恐れが、株式公開市場への上場を躊躇する主な動機となっていた。
複数議決権付株式は、会社の支配権の喪失という代償を支払うことを条件とすることなく、伝統的な金融窓口からではなく、資金調達のため公開市場への上場をという恩恵に授かることを可能とする。
本指令では、2種類の株式を発行する方式を提案する。1種類目は、株主の出資資本に比例して発行し、その資本に比例した議決権を与える株式。2種類目は、各株主に2票、もしくはそれ以上(定款の規定による)の議決権を与える株式。後者の株式の場合、株式の額面金額との比例はない。
複数議決権付株式は、支配株主によって保有される。つまり、株式公開市場買付によって株を取得した他の株主よりも保有株式数が少数の場合でも、複数議決権付株式によって付与される議決権数が多数あるため、引き続き、会社支配を可能とする。
しかし、このメカニズムを採用することは、無議決権株式、いわゆる黄金株と言われる拒否権付株式、さらにTenure voting株式等、株主の権限を強化する他のメカニズムの採用の可能性を排除する。この不適合の帰結として、定款にこれらの他の代替的なメカニズムをすでに定める会社は、複数議決権付株式のメカニズムを承認時に、それらを排除する必要がある。
本指令制定の主目的は、おそらく、EU加盟国内における複数議決権付株式メカニズム規制の足並みが揃わなくなることを、あるいは、ある一部の加盟国がこれを禁止することを防止することであろう。同指令は、そのような加盟国内格差は、結果としてEU市場内の資本の自由移動に対する障壁を生み出すになると主張している。ただし、この意見に批判がないわけではない。後述するように、本指令自体が、複数議決権行使に関する一定の保護装置を設定する余地を加盟国に比較的広範囲に与えており、最終的には各国間で実質的な差異が生じかねないからである。
会社が複数議決権システムを導入しようとする場合の正式要件については、株主総会において特別過半数(una mayoría cualificada:過半数よも高い割合の表決数を定める。通常、2/3以上の過半数) によりこれを決定し、定款に定めなければならない、とした。当該議決権行使システムの採用は、株式のMTFへの登録に先立って有効となる。
複数議決権システムを導入後、本指令は、会社がMTFにアクセスする際に、複数議決権を有効に行使できるようにする条件を、加盟各国が独自に決定できる余地を残している。 当該システム導入意義は、そのような取引市場へのアクセスであるため、合理的であるといえよう。
複数議決権付株式は、記名株式(acciones nominativas)と無記名株式(acciones al portador)の両方で発行できる。 しかし、いずれの場合も、ブロックチェーンを使用して登録された帳簿、もしくは、株式の真実性、変更不能性、トレーサビリティを保証する技術的資源によって表章された分散型台帳技術によって登録されていなければならない。
複数議決権付株式システム導入に反対する者は、当該株式を保有する株主の権力の濫用のリスクを、主な反対理由の一つに挙げる。しかしながら制限や「少数株主保護措置」を設けることは、企業活動や組織体制への不適切な介入といえ、逆に各加盟国間の規制方法に差異を生じさせる可能性がある。 当該保護措置には、強制的と任意的なものの2種類が存在する。
各加盟国が自国法に定めなければならないとする保護措置には、以下のものが含まれる:
A) 加盟国は、1株当たりの最大議決権数(複数議決権付株式に付された議決権数と、それより低い数の議決権を付された株式の議決件数間の最大比率)を定めなければならない。しかしながら、本指令は具体的な範囲、数を定めておらず、各国の裁量に委ねている。
B) 上記と代替的、あるいは累積的に、加盟国自国法に則り特別決議を必要とする決定については、複数議決権の行使を制限するものとする。このような場合の過半数は、発行株式および株主総会に代表される株式資本の特別過半数、
または、発行株式および議決権に影響を受ける株式の種類ごとの行使を伴う特別過半数による決議でなければならない。
経営陣の選任・解任、経営や監督に関する決定などのように特別過半数を必要とする業務上の決定の際には、このような強化された複数議決権の適用から除外することをここで指摘することは重要であろう。
加盟国は、自国の裁量に基づき、複数議決権付株式の消滅に関し、サンセット条項とも呼ばれる消滅条項等も含むその他の保護措置の設定を導入することができる:
(a)生前贈与や死後贈与といったケースを問わず、 複数議決権付株式譲渡時の消滅条項
(b) 本指令には特定の期限を定めてないが、時間の経過に基づく消滅条項
(c) 特定の状況または事実発生に基づく消滅条項。
(d) その他条項は、加盟国が基準を定める。本指令は保護措置の数を一律に定めておらず、第4条第2項に、例として3つの条項が挙げられているのみだからである。
本指令の前文(19)には、複数議決権付株式に付随する追加の議決権は、会社が、EUの定める環境法制、もしくは基本的人権の尊重遵守を妨げるような件の決定には使用できないと記している、しかし、この曖昧な表明は、最終的に同指令の条文内で具体化されなかった。故に、当該記述は、最終的に義務として定められるような場合には、複数議決権メカニズム導入目的に与えるであろうネガティブな影響は別として、EU加盟国に対し拘束力のない、観念的性質を有す規定上のジェスチャーとして解釈されなければならない。
最後に、複数議決権付株式システム制度導入を決定した会社が遵守すべき、透明性、もしくは知る権利に関連する義務を以下にいくつか記す。
(i) 中小企業用株式市場への目論見書および年次財務報告書において、会社の株式構成 を具体的に記載し、株式の種類、その権利と義務(上場が認められるものとそうでないものの両方)、 株式総数およびその議決権を詳述すること。
(ii) 株式譲渡に制限がある場合には、制限があることを記載した株主間契約の条項を提示すること。
(iii) 会社の議決権の5%以上に該当する複数議決権付株式保有株主または議決権行使 代理人の身元に関する情報を伝えること。
(iv) 市場取引が認められている複数議決権付株式メカニズムを導入会社の識別を、市場運営者が行うこと。本指令の前文(18)において言及があるが、方法について具体的な指示がなく、欧州委員会が促進する将来のプロジェクトに委ねている。
本指令は、遅くとも2026年12月5日までに加盟各国が自国の法律に移管する必要がある。しかし、実務面での市場への影響、とりわけ、複数議決権付株式メカニズムを導入を決定する中小企業の経営強化に与える影響は、一見では明らかではない。中小企業への実質的な支配者である自然人の性質の特異性、特にスペインの場合、大多数の中小企業が閉鎖的な家族経営であることを考慮すると、EU内で均一な影響を及ぼすことはないように思われる。上記は、このメカニズムが、支払い能力や担保力の面から従来の方法では資金調達が困難であるが魅力的なプロジェクトを有す設立直前、もしくは設立間もない中小企業が、多国間融資制度の枠組みの中(比較的ローコストで)ハイリスク・ハイリターンを受け入れる投資家による資金調達を容易する現実的な方法であることを妨げるものではない。
ヴィラ・エドアルド (Eduardo Vilá)
ヴィラ法律事務所
更なる情報を知りたい方は以下までご連絡下さい。
2024年11月22日