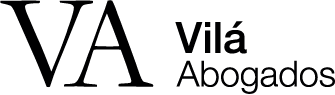導入部
債権譲渡とは、旧債権者から新債権者への債権の移転を可能とする法的、および商取引上の重要な手法である。
スペイン法は、債権譲渡の有効性成立には債務者の同意は不要とし、通知のみで十分とすると明示的に定める。ただし、債務者の同意を無意味と位置付けるわけではない。この点において、商慣習および判例は、債務者同意がもたらす効力を正確に測る必要性、特に債務者が新債権者に対して抗弁する可能性に関して、その必要性を強調してきた。
直近の2025年7月15日付スペイン最高裁判所判決第1123/2025号(以下「本判決」という)は、この点に関する、債務者が債権の譲渡に同意した場合の効力、新債権者に対する抗弁権の喪失、といった疑問を解消するものであった。本稿では、本判決、及びその実務上の商業取引における影響について分析する。
スペイン法体系における債権譲渡
当事者間合意にて異なる定めがある場合を除き、スペインにおける債権譲渡自由の原則は、民法第1123条、第1198条、第1203条第3項、第1526条以下、および商法にこれを定める。第三者譲受人(新債権者)による債権の取得は、元の債務関係の義務内容を変更するものではなく、単に債務関係における債権者の交代を意味し、債務者は新債権者に対して同一の条件で債務を負う。(債務者に対する債権譲渡の客観的中立性)。
債務者に対する債権譲渡通知
譲渡の有効性について、債務者の同意は不要であり、譲渡人、譲受人間の合意のみで十分である。債務者への通知は、主に対抗要件、および債務者の善意の保護を目的としたもので、債務者が譲渡の事実を知らないうちに旧債権者に対して行った弁済は、その債務を完全に免除するとする。(スペイン民法1526条及び1527条規定)。これらの性質は、債権の流通を促進するとともに、債権の所有権者の変更に伴う債務者の法的地位を保護することを目的として判例法上確立されている。
債権譲渡への債務者同意の効力
上記に関わらず、債務者の同意は瑣末なものは言えず、その効力を有す。具体的には、民法第1198条は、債務者が債権譲渡に明示的に同意した場合、債務者は譲渡人に対して有する債権の相殺を、譲受人には主張できないと定めている。この例外は、債務者、旧債権者ら当事者間の個人的な関係に特に関連しているものとされている。一方、債務者の同意がない場合は、通知後の場合でも、債務者は譲渡前の債権に対する相殺を主張する権利を有する。
民法は、債務者が新債権者に対し主張可能な抗弁権に関する債務者の譲渡同意の効力について、上記の規定のみを明示的に定める。しかしながら、各事案における状況や、同意に至る条件は、新債権者に対する将来的な抗弁権の効力において依然として重要な要素となる。したがって、体系的な解釈や他の一般規定から、他の効力が導き出される可能性もある。
その中で最高裁判所は、債務者の同意は、将来の抗弁権の放棄として有効に機能し得ると認めている。例えば、債権譲渡に債務者が明示的に同意した場合、本同意には、将来的に譲受人に義務の履行を要求された際に、すべて、または一部の抗弁権を放棄する自発的な放棄を含む可能性がある。当該放棄は、民法第6条2項および関連する判例法に定める要件を満たす場合、有効される。すなわち、除外(放棄)は自発的であり、公共の利益や秩序に反せず、第三者に損害を与えない場合にのみ有効であるとする。
同様に、当該同意は、同意時にすでに有していた抗弁権を後日主張する可能性を制限する効力も有し、機会を有していたにもかかわらず、何らの表明も行わなかった場合にも適用される。
争点:債権譲渡に対する債務者の単純同意の範囲
直近判決で議論された争点は、債権譲渡についての債務者の単純同意が、単に相殺の主張を排除する(民法第1198条規定)だけでなく、契約不履行、債務の不在、または契約不適合の場合など、他の客観的または個人的な抗弁権の放棄を意味するかどうかを明確にすることにあった。
民法第1198条の文言は、同意時に付与される唯一の特定の効力は相殺の排除であるとしている。当該効力を他の抗弁に拡大することは、本判決の具体的な事例において上告人(債務者)が主張したように譲渡対象債務者の状況悪化をもたらさないという原則に反することになる。
2025年7月15日付スペイン最高裁判所判決第1123/2025号
本判決は、供給契約に基づく債権譲渡事例に起因するものであった。債務者は、債権譲渡の通知を受領、同意後に、商品の引渡しがされていないことを理由に、譲渡債権に呼応する請求書の支払いを拒否した。第1審、第2審判決は、譲渡同意が、相殺を超えて客観的かつ個人的な抗弁権を放棄するものと解釈した。しかしながら最高裁判所は、両判決を破棄し、上告人(債務者側)の主張を認める判決を下した。その理由として、債権譲渡は債務内容を変更するものではなく、単に債権者の所有権を変更するものであることを指摘した。
義務関係の不可変性の原則
義務関係は、その本質的な要素において一切変更されないため、債務者の同意は、民法1198条に明示的に規定する相殺を除き、債権者に対する債務者の一切の抗弁権の無制限な放棄と解釈されることはない。したがって、債務者は、譲受人に対して、基礎となる関係から生じる例外を主張する権利を保持する。例えば、対価の欠如、債権の発生原因となる契約の不履行、または請求された義務そのものの存在しない場合などが該当する。
最高裁は、譲受人は旧債権者よりも「より優位な権利」を獲得するのではなく、その利点と制限を含め正確に同等の債権を取得する、と表明した。したがって、新債権者は、債権の根拠となる契約関係の性質およびリスクを事前に調査し、単なる譲渡により法的地位が向上するわけではないことを認識して行動しなければならない。
最高裁による判例上の原則
本判決は、商取引の実務上、以下のような重要且つ明確な原則を確立する:
– 債権譲渡への債務者の同意がある場合、明示的な放棄がない限り、債務相殺以外の抗弁権を放棄したものと解釈されない。
– 客観的もしくは個人的な抗弁権の喪失には、新債権者に対する債務者の明示的かつ具体的な放棄を要し、債権譲渡の通知後の単純同意だけでは不十分である。
– 本判決の具体的事例において、債務者が債権譲渡および当該債権に対応する請求書の適正性を確認したことは、債務者が、契約不履行を理由に新債権者の請求する支払いの拒否を主張する権利を黙示的に放棄したと判断するに足る行為ではない。
実務上の影響および提案
最高裁は、本判決により、債務者の債権譲渡への同意は、民法第1198条の相殺の放棄等、法律に定める効力のみを生じさせる、という明確な法理を確立した。ただし、民法第6.2条およびその判例法に従った明示的かつ有効な放棄がある場合はこれを除外する。
つまり、明確、明白かつ公序良俗に反せず、第三者に損害を与えない意思表明のみが、新債権者に対する債務者の抗弁権の制限を可能とする。
新債権者に対する債務者の防御権を不当に制限する広範な、あるいは黙示的な解釈を回避することで、本件でスペイン最高裁判所が確立した法理は、商取引上の法的安定性を強化する。
実務上は、経済主体が債権の譲渡を文書化する際に特に注意を要す。反する有効な合意がある場合はこの限りではないが、債務相殺以外のいかなる抗弁権を放棄する旨の明示的な記録を残すことが求められる。
債権の譲受人(新債権者)には、譲渡対象である債権の状態および潜在的な問題点の適切な確認を推奨する。なぜなら、義務関係の不変性により、対象債権から生じるリスク負担を義務付けられるためである。ただし、有効合意がある場合は除外される。
結論
2025年7月15日付スペイン最高裁判所判決第1123/2025号は、債務者が債権譲渡に同意した場合でも、その同意自体が、法律に定める条件に基づく相殺を除き、新債権者に対する抗弁権を放棄するものでないことを明確にした。
当事者の明確な行動基準の制定をする当該法理は、債権譲渡取引における法的安全性を高める。これにより、債権流通を促進するという商取引上の法的目的、および新債権者からの債務者の正当な権利保護の必要性との間で、適切なバランスを保つことが可能となる。
フリオ・ゴンサレス (Julio González)
ヴィラ法律事務所
より詳細な情報につきましては下記までご連絡ください。
2025年8月22日